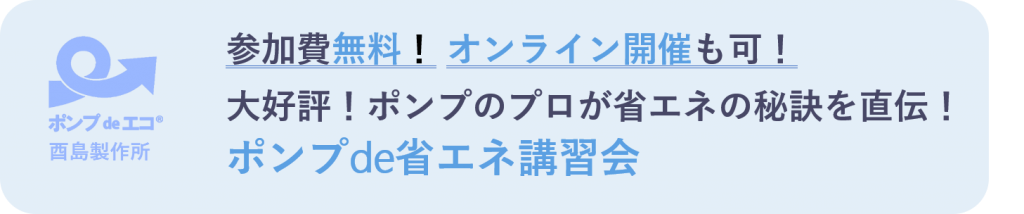ポンまるがわかりやすく解説します!
(1)はじめに
1.jpg)
こんにちは、ポンまるです!
突然ですが、皆さん「鋳造(ちゅうぞう)」って
ご存じですか?
実は、私たちのポンプに使われている
ケーシングやインペラも、
この鋳造という方法で作られています。
今回は、「鋳物(いもの)」や「鋳型(いがた)」といった
鋳造にまつわる基本用語を
わかりやすく説明していきますので
一緒に学んでいきましょう!
(2)鋳造とは?

金属で何かを作りたい時、
いくつかの方法が考えられます。
切削や溶接などもありますが、
金属の形を変えるのって
実はとても大変なんです。
特に固い金属をそのまま加工するには、
すごく大きな力が必要になってしまいます。
ここで登場するのが「鋳造」です!
鋳造は、金属を一旦溶かして液体状にしたものを「鋳型(いがた)」に流し込み、
そのまま固めて形を作る方法です。
…「鋳型?」と疑問に思った方も安心してください。
これから順番に説明しますね。
- 溶湯(ようとう)
金属を溶かしてドロドロにしたもののことです。 - 鋳型(いがた)
溶かした金属を流し込むための型で、欲しい形の空間が作られています。 - 鋳込み(いこみ)
この溶湯を鋳型に流し込む工程を指します。 - 鋳物(いもの)
最終的に固まって完成した金属製品のことをこう呼びます。
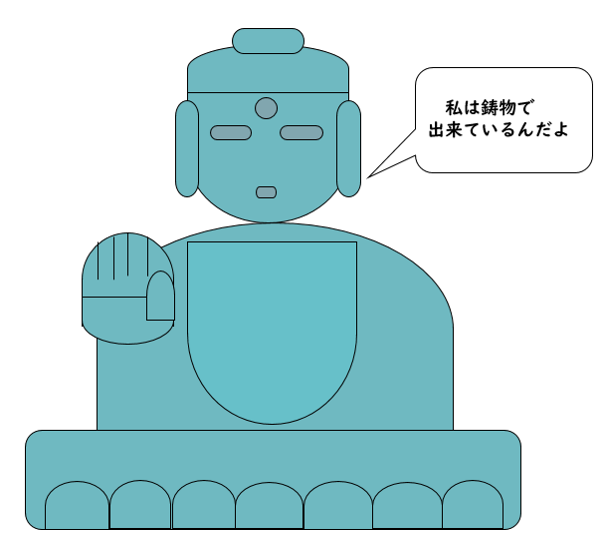
ところで、奈良の東大寺にある
有名な大仏も、
この鋳造技術で作られているんですよ!
高さ約15メートルの大仏を、
なんと奈良時代に鋳造で仕上げたんです。
当時からすでに鋳造技術が
確立されていたなんて驚きですよね。
(3)おわりに
ここまで、鋳造について簡単に説明しましたが
文字や写真だけではイメージが湧きにくいかもしれませんね。
もし興味があれば、ぜひ私たちの講習会にお越しください!
酉島の工場で実際の鋳造の流れや鋳物がどのように作られているのか、
直接見ることができます。お待ちしています!